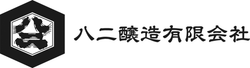東北最古の会津本郷焼
今から400年以上も昔である安土桃山時代の1593年、会津若松城(鶴ヶ城)主・蒲生氏郷が城の改修のために播磨国(兵庫県)から瓦工を招き、瓦を焼かせたのが発祥といわれているのが会津本郷焼です。
その後、1645年に会津藩主・保科正之が招いた美濃国瀬戸(現在の美濃焼)出身の陶工・水野源左衛門が本郷村に良い土を発見し、窯場を構えたのが会津本郷焼の陶器の起源といわれております。
そして、会津藩が本郷に奉行所を置き、藩の産業として会津本郷焼に力を入れておりましたが、奉行所の廃止により職人たちがそれぞれの窯を築き、全盛期は100を超える窯元があったそうです。

会津本郷焼の可能性を広げた「樹ノ音工房」
現在は個性豊かな12の窯元が「会津本郷焼」を次の世代へ受け継いでいくという一貫した想いを持ちつつ、それぞれが多種多様な考え方や方向性を持ちながら、作品を生み出し続けています。
その中のひとつである「樹ノ音工房」は、佐藤大樹、朱音夫妻が2001年に開窯し、「しのぎ」と呼ばれる美しいストライプと柔らかな手彫りの模様と、カラフルな絵付けの作品が特徴で、若者層に本郷焼のファンを一気に広げた窯元です。

八二醸造限定カラーの醤油皿
今回、「会津特産品プロジェクト」として、会津本郷焼の魅力を発信したく、飛び込みで窯元を訪れてお話させて頂きました。そして、醤油蔵ならではの「醤油皿」を作成して頂けることになりました。
1点1点、手作業で色付けをしておりますので、醤油皿の枚数だけ表情の異なる起き上がり小法師が描かれております。会津観光のお土産品として、実際にお手に取って頂き、お気に入りの一枚を食卓に迎えて頂ければ幸いです。
<参考>
会津本郷焼, https://aizuhongouyaki.jp/
会津本郷焼 樹ノ音工房, https://www.kinooto.com/